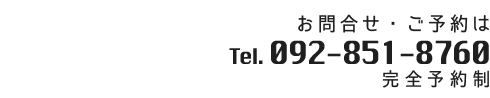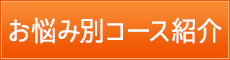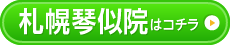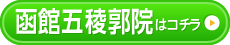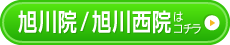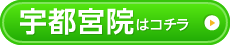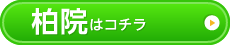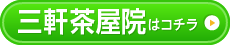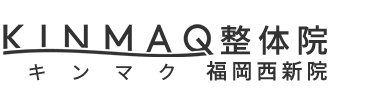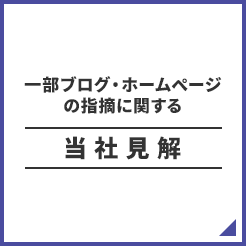肩こりの原因になるものは1つではなく、様々な要素が関連しております。
その中でも今回は呼吸と肩こりについてお話ししていきます。
まずは、呼吸を司る筋肉についてです。
呼吸に関連する筋肉は主に4つあり、横隔膜・肋間筋・肋骨挙筋・斜角筋があります。
それらを補助する呼吸補助筋と呼ばれる筋肉も存在します。
その筋肉は胸鎖乳突筋・僧帽筋上部・前鋸筋・広背筋・上後鋸筋・鎖骨下筋・肩甲舌骨筋などがあります。これらの筋肉は首回りに付着している筋肉が多く、メインの呼吸筋の働きが悪くなると、呼吸補助筋が過剰に使用されやすくなるため、首~肩周りの筋肉が固まってきやすくなります。呼吸は1日に3万回しており、休むことなく活動しているため、呼吸補助筋の過剰使用が毎日続くと筋肉にも負荷がかかり、慢性的な肩こりへとつながってしまいます。
では、呼吸パターンとしてどのようになるのが良いのでしょうか?
一度ご自身の呼吸を観察してみてください。
仰向けに寝た状態で自然に呼吸を行った際にどこが一番膨らみが出ていますか?
1番良い呼吸方法はお腹と胸が同じタイミングで同じくらい膨らむ呼吸が良いです。
息を吸う時に首回りに力が入るのを感じる方や、胸やお腹の膨らみが少ない方は呼吸補助筋を使用した呼吸パターンの可能性がかなり高いです。
これを改善するために、自分のお腹と胸のあたりに手を置き、両方が同じタイミングで膨らむようにして正しい呼吸を反復練習することで学習させることが重要です。
必ず意識してほしいことが頑張って呼吸するのではなく、自然に呼吸をすることです。
特にデスクワークの方は肩こりでお悩みの方も多いかと思います。
その中で意識してほしいことが2つあります。
1つ目は、普段の姿勢です。理想的な座り姿勢としては横から見た時に耳たぶ・肩・骨盤が一直線になるような姿勢が望ましいです。普段からこの姿勢を意識することは非常に大切です。しかし、脊柱はいろんな形状に変化できることが本来の役割であるため、良い姿勢であっても同じ姿勢を取り続けないことも重要です。
2つ目にパソコンと自分の位置や距離を適度に変えることです。
ある一定の距離をずっと見続けていると段々正しい距離感を認識できなくなってしまいます。そうなると頭が前方へ出てきてしまい、それを支えるために頸部の筋肉が過度に働きます。首回りの呼吸補助筋を過剰に使いやすい状態にさらに、頭部の重みを支えるために頸部の筋肉が緊張状態になるとかなり負担になることは容易に想像できるかと思います。
30分に1回は遠くをみるように意識してみてください。
これだけでも負担の軽減につながりますので、ぜひやってみてください!