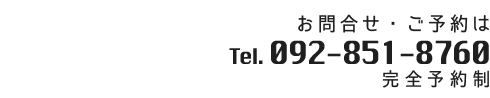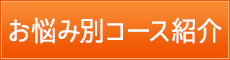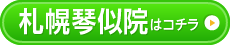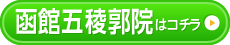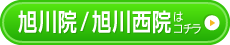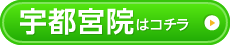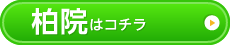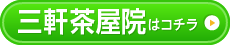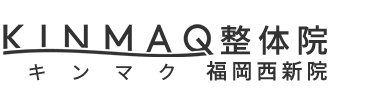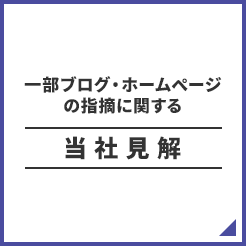前回はパターン別の優先順位について解説していきました。
今回は体幹についての役割をご紹介していきます。
まず、人間の質量割合はどう占めているのかご存じですか?
頭の重さはボウリング球くらいの重さと聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
実際の割合を見てみると体幹は約半分の46%も占めているのがわかります。
その次に頭部が8%、大腿部が7%、下腿が6%という順番になっており、この数値をみると体幹の占める割合がかなり多いのが感じ取れるかと思います。
そんな体幹を支える骨は脊柱と呼ばれ、脊柱は3つに分けられます。
頸椎・胸椎・腰椎に分類され、頸椎7個、胸椎12個、腰椎5個の骨からなります。
脊柱は3つのカーブがS字状に形成されており、その弯曲には重要な役割があります。
S字カーブがバネの役割を担い、あらゆる負荷に対して衝撃を吸収する作用を持っています。
3つのカーブが1つ減って2つになると衝撃吸収能力が半分になります。さらに減って1つのカーブのみになると5分の1まで減少してしまいます。最終的に弯曲がなくなって真っすぐの状態になると10分の1にまで減少してしまいます。
そのため、1つでも弯曲構造が破綻してしまうと本来の能力の半分以下になってしまうということなんです。
その弯曲構造は筋肉での支えがあってこそ成り立っています。年齢と共にだんだん筋力の衰えが起きてくると筋肉での支えがなくなり、不安定な状態になってきます。
不安定な状態になると一本の柱のように支柱を作った方が安定性は高くなるため、脊柱の構造が次第に真っすぐになっていきます。
安定性は高まる一方、衝撃吸収能力が低下してしまいます。
そうなるとあらゆる負荷が身体の中に蓄積していき、痛みや痺れなどの不調が出現していきます。
そのため、体幹のインナーマッスルを使えるようになること・脊柱の動きが正常に行えることが非常に重要です。
前項のパターンによっては筋肉量が多くても、脊柱の動きが硬くなったり、全身の柔軟性が低下していると上手く力を引き出せていない可能性もあるので両方へのアプローチをすることで相乗効果が期待できます。
では、次回は体幹へのアプローチについてより詳しくご紹介していきます!