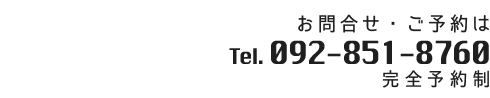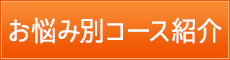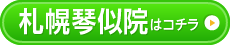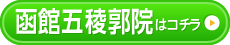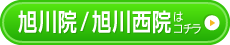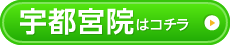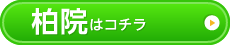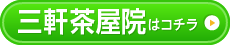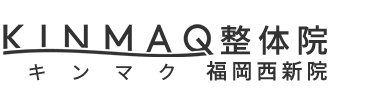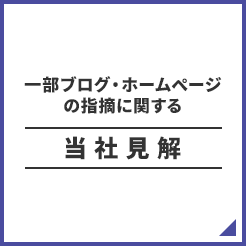今回は姿勢のタイプ分けと頭部の位置関係についてお話ししていきます。
今回は姿勢のタイプ分けと頭部の位置関係についてお話ししていきます。
以前姿勢のタイプ分けについて掲載した内容にもなりますが、姿勢には大きく分けて正常・円背・腰椎過前弯・フラットバック・スウェイバックの5つにタイプ分けされています。
その中でも円背・フラットバック・スウェイバックの姿勢の方は特に頭部が肩の位置より前方に位置している(頭部前方突出)ことが多いです。
この姿勢をとっていると、ストレートネックや首・肩こり、手の痺れなどが起こりやすくなってしまいます。
頭部前方突出の状態になると身体の中で起こる変化についてお伝えしていきます!
頭部が前方へ位置してしまうことで、正常の姿勢と比べて頭部と肩の位置関係が崩れてしまいます。それによって首や肩関節周囲の筋肉のバランスに変化が起こってしまいます。
その変化としては柔軟性が低下しやすくなる筋肉と筋力が弱くなって使いづらくなる筋肉の2つが出てきてしまいます。
柔軟性が低下しやすい筋肉は主に後頭下筋群・肩甲挙筋・僧帽筋上部などの頭から首の後ろの筋肉や胸鎖乳突筋・斜角筋・小胸筋・大胸筋などの首の前方や胸の前側の筋肉が挙げられます。
使いづらくなる筋肉は僧帽筋下部・前鋸筋などの背中の筋肉や椎前筋群(頭長筋・頸長筋)などの首の前方にある筋肉が挙げられます。

悪い姿勢になり頭部前方位のままデスクワークを長時間したりしていると、首の後ろの筋肉や首から肩にかけて付着する筋肉の柔軟性低下が起こり、肩こりなどにつながります。
また、胸の前側の筋肉も硬くなることで猫背が強くなり、胸を張るような動作がやりづらくなります。そうなることで猫背が段々と強まり、さらに頭部と肩の位置関係の崩れが生じて、首や肩回りの不調が強くなってしまいます。
使いづらくなる筋肉の中には頸部のインナーマッスルや肩甲骨を安定させるための筋肉が多く含まれています。そのため、頸部インナーマッスルの弱化によって首が不安定な状態になり、その不安定な状態を支えるために首~肩周囲の筋肉が過緊張状態になります。
僧帽筋下部や前鋸筋は肩甲骨を安定させるために不可欠な筋肉ですが、使いづらくなるとその筋力を補うのが僧帽筋上部や肩甲挙筋などの筋肉があり、これを繰り返し悪いパターンで動かしていると肩こりの原因になってしまいます。
この頭部前方突出を修正するためには、姿勢から変化させることが重要です。
姿勢からしっかり修正していきましょう!